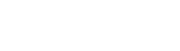よみがえる古民家(2)
よみがえる古民家(2)
再生目的の解体は、建築順と逆をたどる。まず雨戸、障子、ふすま、などを取り外す。古民家には吟味された材料に凝った細工を施した建具が多いいのだけれど、高さがゴハチ(5尺8寸≒1757㎜)なので再利用は難しい。通り抜けしない押入れなどにはそのまま利用可能だが場所は限られてしまう。下駄をはかせて利用したのを見かけるが、デザイン的には極めて不自然だ。次に屋根を解体し、壁を落とす。壁を先に剥ぐと屋根がぐらついて危険だ。骨組みだけにしたら正確に番付けをふり、継手や仕口を傷めないように丁寧に取り外す。大工の加工には墨切り・墨残しと言う口伝がある。一ミリにも満たない差が、建築の強度に影響するからである。古民家を解体していると、正確な加工が施されていることがわかる。墨切り・墨残しの口伝が生きているのだ。驚くのは正確さだけでない。思いがけない継手・仕口、達者な墨書が出てくる。こんな出会いがあると、棟梁の技量のみならず現場の雰囲気までも伝わってくるようでとても楽しい。
しかし、古民家の魅力は何と言っても材に刻まれた手斧(チョウナ)の痕だ。リズミカルに波打つ手斧の痕が、光の陰影をつくり一本一本が芸術品とも呼べる梁や桁になっている。このような梁や桁をいかに再生するかが設計者の力量だ。解体にかかわってこそ、本来持っている古材の魅力を生かせると信じているので、筆者は常に先頭に立って解体する。だが、手作業はいつも危険と隣り合わせだ。思いもかけぬ方向に跳ねた梁が頭の十数センチ先をかすめていったのは写真の現場だ。「命を拾った」解体現場から困難極まる再生の現場に次回はご案内いたします。「自然の権利」基金通信vol.62 掲載